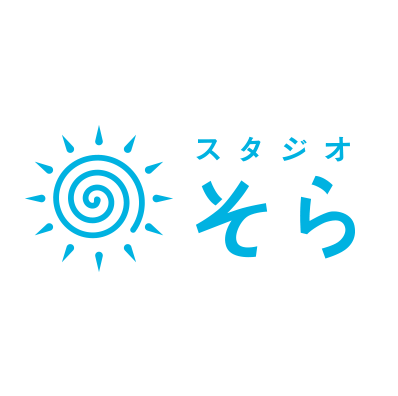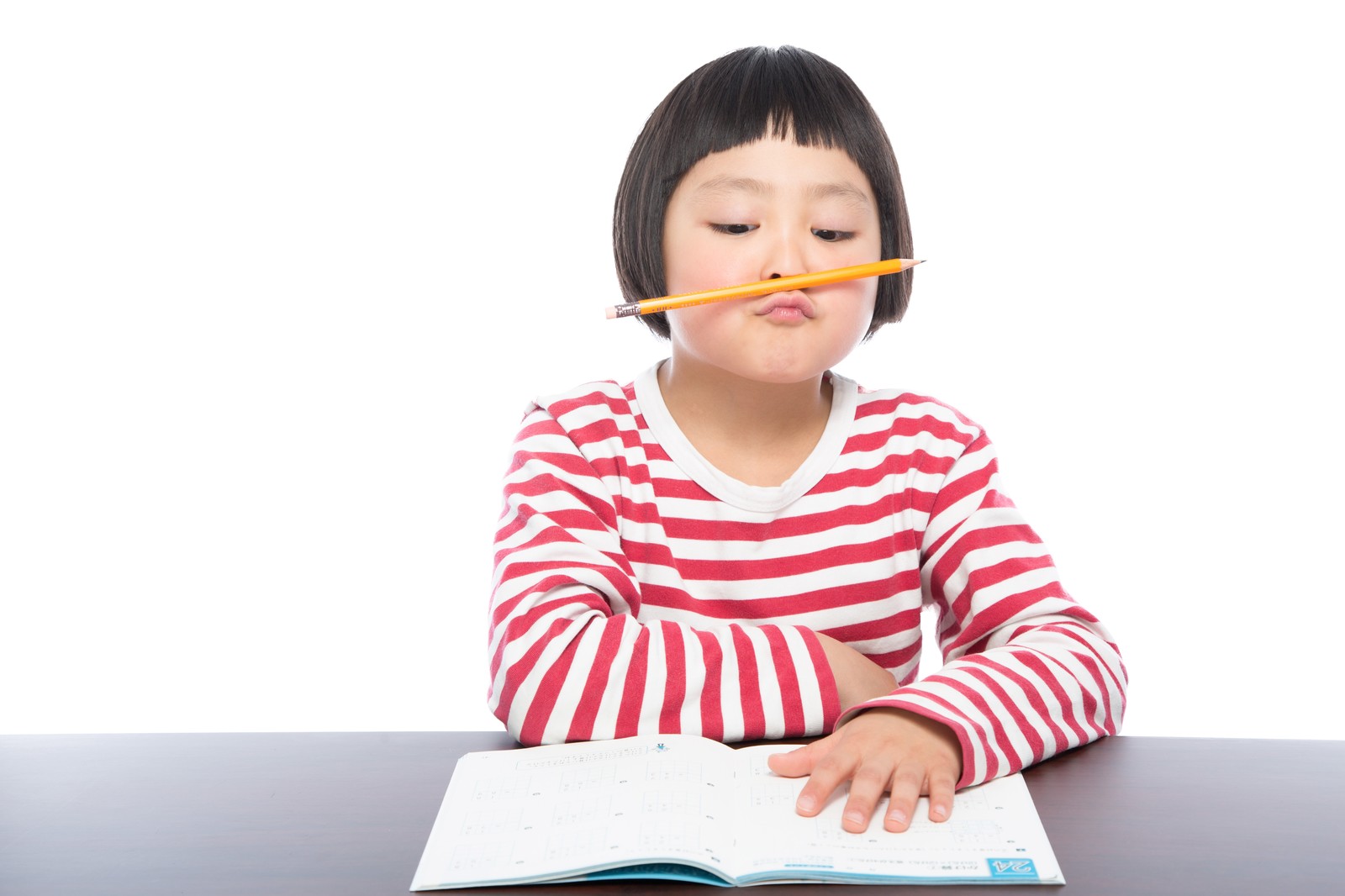子どもの発達障害を早期発見するためのチェックポイント
2018.11.12発達障害のある子どもの早期発見の手がかりとなる時期には、3歳健診や5歳健診があげられます。さらに、幼稚園や就学してからなど、集団生活を過ごすようになってから、気になる行動が多くみられる場合もあります。
今回は子どもの発達障害を早期発見するためのチェックポイント(子どもの気になるサイン)を紹介します。
~気になるサイン~(37項目) (田中,2016)
・泣かない/ほほえまない
・人と目を合わせない/名前を呼んでも振り向かない
・言葉が遅い/発語が喃語ではない
・指さしをして注意をひかない/言葉で気持ちを伝えない
・音や肌にふれるものに敏感/手をつなぐ、抱きしめられるのを嫌がる
・偏食が強い/味やにおいに敏感
・親から離れてしまう/迷子になっても平気
・ひとりで遊ぶことが多い/友達の輪に入らない
・同年齢の友達ができない/人付き合いがうまくいかない
・独特の話し方をする/おしゃべりが止まらない
・こだわりや特定のものへの執着がみられる
・一度に複数のことをするのが苦手
・行事に参加できない/集団行動や共同作業ができない
・変化を楽しめない/変化についていけない
・気持ちがうまく切り替えられない
・同じ手の動きを繰り返す/手のひらをヒラヒラさせる
・言葉や会話の含みがわからない/冗談が通じない
・空気が読めない/人の表情が読めない
・寝付きが悪い/すぐ目が覚める
・前ぶれなく怒る/その場にふさぎこむ
・表情が直接的/あいまいな表現が苦手
・昔のことを昨日のことのように話す/終わりがわかりにくい
・パニックを起こす
・姿勢の崩れがみられる
・嫌がったり、不安になったりすることが多い
・ルールを守れない/順番を待つことが苦手
・すぐ行動してしまう/事故にあいやすい
・忘れっぽい/細かなところに注意が向かない
・集中できない/じっとしていられない
・反抗的な態度をとる/悲観的な感情を抱きやすい
・他の子を突き飛ばす/たたく、ける/特定の子どもを泣かす
・文章を読み間違う/誤った文字を書く
・話をきくことが苦手/話すことが苦手
・計算や図形の理解、推論することが苦手
・手先が不器用/指先の力が強すぎたり、弱すぎたりする
・全身運動が苦手/自分の身体がわかりにくい
これらの項目に当てはまるからといって必ずしも、発達障害の特性をもっているということではありません。
子どもは幼い時には、他のものに気を取られやすかったり、落ち着きがなかったりすることも多いため、気になるサインが見過ごされてしまうこともあります。しかし、「どうしてこの子はこうのような発言・行動をするのだろう?」「他の子と違う」などと疑問に思う点や日常で困ることが多い場合は、児童精神科や小児精神科、子どもの発達に詳しいクリニックなどに相談してみましょう。専門機関では診察を受けるのに時間がかかることもありますので、地域にある子育て支援センターや保健師さんなどに相談してみるのもおすすめです。
子どもが様々な形で出している日常の困っているサインが、「変わっている子ども」と周囲に捉えられてしまうことがあります。もしくは子ども自身が「みんなとどこか違う」「自分だけできない」などと違和感を感じている場合もあります。なるべく早めに本人の困り感に気づいてあげることで、その後の支援に繋がる場合もあります。
<引用・参考文献>
田中康雄(2016)「発達障害の子どもの心と行動がわかる本」西東社.